MT*2_25-払田柵跡について二、三の考察/山形県本楯発見の柵跡について 喜田貞吉
2010.1.9 第二巻 第二五号
払田柵跡について二、三の考察
山形県本楯発見の柵跡について ——出羽柵跡か国分寺跡か——
一 緒言
二 本楯柵跡の型式と規模
三 出羽柵跡はこれを河南に求むべく、本楯柵跡は出羽柵の廃虚にあらず
四 本楯柵跡は出羽柵としては狭小に過ぐ
五 本楯柵跡は出羽柵としては型式的にして、防御設備薄弱に過ぐ
六 本楯柵跡は国分寺の外郭の廃虚なるべし
七 結語
喜田貞吉
imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。
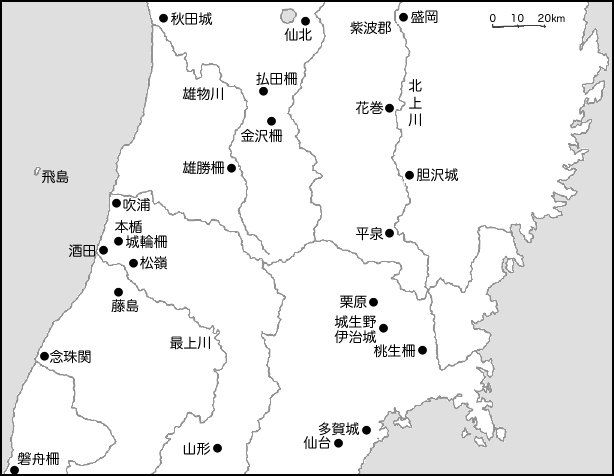
| 定価:200円(税込) |
p.172 / *99 出版 |
付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(81項目)p.432
飛び出せ! 目くそ鼻くそ!
| オリジナル版 |
ミルクティー*現代表記版 |
| 払田柵址について二、三の考察 |
払田柵跡について二、三の考察 |
| (略)由来わが国には大陸にいわゆる城郭は発達しなかった。シナの古代史籍にも、国城郭なしと書いてあるのが普通である。いわゆる城郭とは村落都邑全体を擁護すべく設けられたもので、わが国にいわゆる城砦とは違う。わが国の城砦は太古の夷砦《チャシ》式のものから、近く戦国時代の大小名の城池に至るまで、たいていは豪族の居館に防禦工事を加えたものなるに過ぎない。斉明天皇の御代に飛鳥帝都の背後の山なる多武峯に石をもって周垣を築くのことが『日本紀』にあるのは、おそらくわが国における朝鮮式山城の最初のものであろう。天智天皇の御代には外寇に備うべく所々に大陸風の城郭が出来た。かくて「大宝令」には、東辺・北辺・西辺における諸郡の民居は城堡の中に安置せよとの規定が法文に示されている。蝦夷・隼人に対して、大陸風の村落保護の設備なのだ。西辺のことは措く。東辺・北辺すなわち陸奥の蝦夷・越蝦夷の地方にもだんだん内地の農民が進出する。それが蝦夷の襲撃を防ぐために集落を繞って防禦工事を施す。これが「大宝令」にいわゆる城堡なのだ。かくて平素はその中に安住し、農時には臨時に田屋住居をする。後に蝦夷襲来の虞れがなくなって、田屋が発達して各地に農村が散在するようになった。この払田の地は仙北平野の中央にあって、そこには真山・長森の丘陵があり、この平野に進出した内地農民の根拠地としてはきわめて適当の地だ。今の柵址はそこに設けられた集落擁護のために、取り敢えず造られたものと解するのが最も妥当であろう。 |
(略)由来わが国には大陸にいわゆる城郭は発達しなかった。シナの古代史籍にも、国城郭なしと書いてあるのが普通である。いわゆる城郭とは村落都邑(とゆう)全体を擁護(ようご)すべく設けられたもので、わが国にいわゆる城砦(じょうさい)とは違う。わが国の城砦(じょうさい)は太古の夷砦(チャシ)式のものから、近く戦国時代の大小名の城池にいたるまで、たいていは豪族の居館(きょかん)に防御工事を加えたものなるにすぎない。斉明(さいめい)天皇の御代(みよ)に飛鳥帝都の背後の山なる多武峰(とうのみね)に石をもって周垣(しゅうえん)を築くのことが『日本紀(にほんぎ)』にあるのは、おそらくわが国における朝鮮式山城(やまじろ)の最初のものであろう。天智(てんじ)天皇の御代には外寇(がいこう)に備うべく所々に大陸風の城郭ができた。かくて「大宝令(たいほうりょう)」には、東辺・北辺・西辺における諸郡の民居は城堡(じょうほう)の中に安置せよとの規定が法文に示されている。蝦夷(えみし)・隼人(はやと)に対して、大陸風の村落保護の設備なのだ。西辺のことは措(お)く。東辺・北辺すなわち陸奥の蝦夷・越蝦夷の地方にもだんだん内地の農民が進出する。それが蝦夷の襲撃を防ぐために集落をめぐって防御工事をほどこす。これが「大宝令」にいわゆる城堡(じょうほう)なのだ。かくて平素はその中に安住し、農時には臨時に田屋(たや)住居をする。後に蝦夷襲来のおそれがなくなって、田屋(たや)が発達して各地に農村が散在するようになった。この払田(ほった)の地は仙北(せんぼく)平野の中央にあって、そこには真山(しんざん)・長森(ながもり)の丘陵があり、この平野に進出した内地農民の根拠地としてはきわめて適当の地だ。今の柵跡はそこに設けられた集落擁護のために、とりあえず造られたものと解するのが最も妥当であろう。 |
 2_25.rm
2_25.rm
(朗読:RealMedia 形式 440KB、3'33'')
喜田貞吉 きた さだきち
1871-1939(明治4.5.24- 昭和14.7.3)
歴史学者。徳島県出身。東大卒。文部省に入る。日本歴史地理学会をおこし、雑誌「歴史地理」を刊行。法隆寺再建論を主張。南北両朝並立論を議会で問題にされ休職。のち京大教授。
底本
払田柵跡について二、三の考察
底本:『喜田貞吉著作集 第一巻 石器時代と考古学』平凡社
1981(昭和56)年7月30日
初出:『秋田考古学会誌』第2巻第4号
1930(昭和5)年12月
山形県本楯発見の柵跡について
底本:『喜田貞吉著作集 第一巻 石器時代と考古学』平凡社
1981(昭和56)年7月30日
初出:『歴史地理』第58巻第1号
1931(昭和6)年7月
NDC 分類:212(日本史/東北地方)
http://yozora.kazumi386.org/2/1/ndc212.html
※ ページ未登録。
年表
大化四年(六四八) 磐舟柵を築く。磐舟柵をおさめてもって蝦夷にそなえ、越と信濃との民を選んで柵戸を置くとあるのを初見。
斉明天皇の御代(六五五〜六六一) 飛鳥帝都の背後の山なる多武峰に石をもって周垣を築く(『日本紀』)。おそらくわが国における朝鮮式山城の最初のもの。
斉明天皇四年(六五八) 阿倍比羅夫が、舟師をひきいて遠く津軽、北海道にまで経営の歩みをすすめる。
天智天皇の御代(六六八〜六七一) 外寇に備うべく所々に大陸風の城郭ができる。
天武天皇十一年(六八三)四月 越蝦夷伊高岐那ら、俘人七十戸(ちなみにいう、天武天皇十一年の俘人七十戸は、現存の『書紀』に七千戸とある。今『釈日本紀』の文に従う)をもって一郡となさんと請うて許さるる。
持統天皇三年(六八九) 陸奥優<IMG gaiji src="山+耆.gif">曇郡の城養蝦夷・脂利古男麻呂が、出家修道を請うてゆるされた(『日本紀』)。
文武天皇二年(六九八)十二月 越後国をして築五十一年目の磐舟柵を修理せしめ、
文武天皇四年(七〇〇)二月 越後、佐渡の二国をして石船柵を修営。
慶雲二年(七〇五) 威奈大村・越後城司に除せられて、北疆の蝦虜の懐柔鎮撫に任じられる。
慶雲三年(七〇六)閏正月 威奈大村、越後守に任ぜらる。墓誌には、その前年十一月、越後城司に除せらるとある。
慶雲四年(七〇七)四月 威奈大村、越後城に卒したと言わるる。
和銅元年(七〇八)九月 はじめて出羽郡が設置。
和銅初年(七〇八) 大宝の度地制がおこなわれて、三百歩すなわち五町をもって一里とした。
和銅二年(七〇九)三月 佐伯石湯を征越後蝦夷将軍とし、紀諸人を副将軍とし、遠江・駿河・甲斐 信濃・上野・越前・越中など、諸国の兵を徴発して、陸奥鎮東将軍たる巨勢麻呂らとともに、東山・北陸両道より蝦夷の征討に向かわしめた。
和銅二年(七〇九)七月条 出羽柵の名の初見は『続日本紀』。朔日、諸国をして兵器を出羽柵に運送せしむ。事実はその以前よりあったと考えられる。
和銅二年(七〇九)七月十三日条 越前、越中、越後、佐渡の四国をして、船一百艘を征狄所に送らしむ。
和銅二年(七〇九)八月 正副将軍入朝して優寵禄をたまわるのことあり。
和銅五年(七一二)九月 越後の北部を分かって出羽国を設置。
和銅六年(七一三) 尺度制改定。後に条里制の実施。
和銅七年(七一四)二月 出羽国をして養蚕せしむ。
和銅七年(七一四)十月 尾張・上野・信濃・越後などの国の民二百戸を出羽柵戸に配す。
霊亀二年(七一六)九月 中納言巨勢麻呂の奏上により、出羽の土地膏腴、田野広寛なるも、吏民少稀にして狄徒いまだ馴れざるがために、随近の国民を出羽国にうつして、狂狄を教喩し、かねて地の利を保たしめんとの請がゆるされて、陸奥の置賜・最上の二郡、および信濃・上野・越前・越後四国の百姓各百戸を出羽国に隷せしめた。
養老元年(七一七)二月 信濃・上野・越前・越後四国の百姓各一百戸を出羽柵戸に配す。
養老三年(七一九)七月 東海・東山・北陸三道の民二百戸を出羽柵に配す。少なくも六年間に八百戸の民は柵内に移された。(『続日本紀』)
天平五年(七三三) 出羽柵、秋田に移る。
天平七年(七三五) 讃岐国の田図、条里に関する史料の現存する最古。
天平十三年(七四一) 「勅」によるに、僧寺には封五十戸、水田十町、尼寺には水田十町。
天平十九年(七四七) さらに増して僧寺水田百町、尼寺五十町となる。
天平勝宝元年(七四九) 僧寺に一千町、尼寺に四百町の墾田をゆるされた。
天平宝字二年(七五八)条 雄勝、柵をつくる。翌年は城をつくる。
承和四年(八三七)六月条 『続日本後紀』小野宗成の請によりて出羽国最上郡に済苦院一処を建立することが聴された。
承和四年(八三七)六月 小野宗成の奏請に対する勅書の文に出羽に国分両寺が見える。その後久しからずして廃滅したものか、『延喜式』諸国国分寺料の項にその名が見えない。
承和六年(八三九)八月 田川郡司の解文に「この郡の西浜府に達するの程五十余里、もとより石なし」。
貞観十三年(八七一) 飽海郡の名の初見。
元慶(八七七〜八八五)夷乱 秋田河をもって華夷の境界とせんとの講和条件まで持ち出された。
延喜(九〇一〜九二三)のころ 国分寺も庄内に求めねばならぬはずである。しかしそれもには廃滅していたらしく。
明治二十年代(一八八七〜) 多くの直立せる掘立柱の根を発掘。
明治四十年(一九〇七)ころ 本楯柵、柱根二個発掘。
大正初年(一九一二) 飽海郡なる遺跡は本楯村城の輪にあり、耕地整理をおこなって、台地を削平して水田となしたさいに、たまたま柱根および廃瓦・礎石などが発見。
大正十一年(一九二二)末 第一次の踏査。
大正十二年(一九二三)一月 喜田貞吉『社会史研究』第九巻第一号所載「庄内見聞録」中に、ほぼその所見を発表。
大正十二年(一九二三) 阿部正巳の東道のもとに実地を視察。
昭和四年(一九二九)末 秋田県仙北郡高梨村払田の地において、延長約一里に渉れる古代の木柵跡の埋没存在せることが、後藤宙外君によりてはじめて紹介。
一九三〇年はじめ 後藤宙外から簡単なる調査の報告を受ける。
一九三〇年四月末 深沢・大山(宏)・大山(順造)・細谷らと、右の後藤君の東道で視察。
一九三〇年五月はじめ 喜田貞吉、浴場で転倒。四か月あまり病床。
一九三〇年十月下旬 文部省から上田三平が出張して柵跡の大発掘を試みる。
一九三一年四月初旬 実地にのぞんで調査の跡を視察。
一九三一年 喜田貞吉「寺院建築と住宅建築、特に掘立柱の発見について」なる一篇を草し、これを本誌(『歴史地理』)前号(第五七巻第六号)に掲載。
一九三一年五月二十三、四日 出羽柵跡大発見の報があったので、まだ水田に水を張らぬ以前にと、余輩はさっそく実地について親しく郷土研究会の方々の調査の跡を拝見。
スリーパーズ日記
9日(土)くもり。NHK山形放送局の大型液晶テレビにて再放送を見る。クレジットに「協力・身延山久遠寺」。ロケ地だろうか。久遠寺=日蓮宗(法華宗)、法華、妙見、北斗、北辰一刀流……勝・西郷の江戸無血開城談判のあったのが同じく日蓮宗の池上本門寺。
10日(日)『アデノゲン』を購入。6800円。『ヘアーグロアーS』『リアップ』『黄金宮』と試してきて、ついに。長らく、裸体で街を歩いているようなはずかしさと冷笑をあびてきたから、自分一人だけが笑い者になるのは、無視すればいいことだからまだたえられる。けれど……。執着のつらさ。メンソールの心地よさ(泣)。
2010.1.12:公開
2010.1.14:更新
目くそ鼻くそ/PoorBook G3'99
翻訳・朗読・転載は自由です。
カウンタ: -
- 『広辞苑 第六版』では、阿倍比羅夫を「あべのひらぶ」、熟蝦夷を「にきえみし」と読んでいる。これまで、同様の読みを他に見た経験がないので、それぞれ慣例のまま「あべのひらふ」「にぎえみし」としておく。 -- しだ (2010-01-14 00:18:07)
最終更新:2010年01月14日 00:18

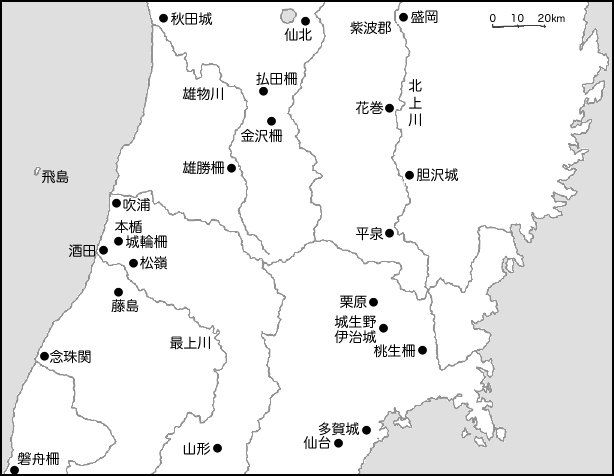
 2_25.rm
2_25.rm